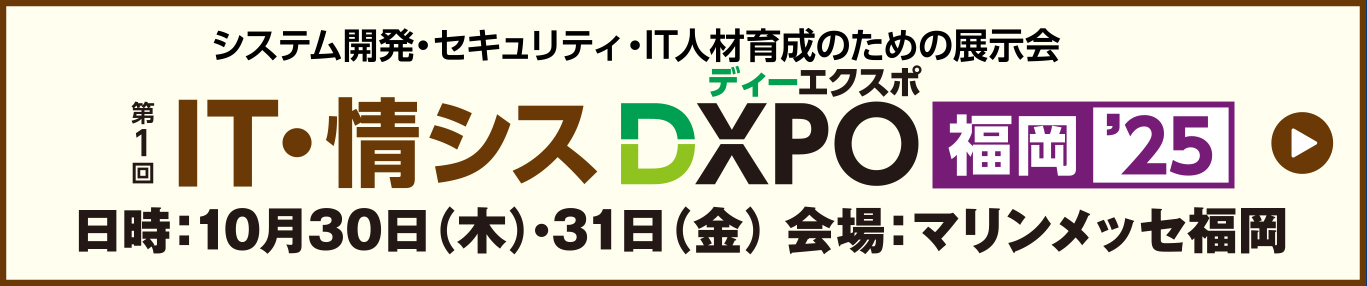AIは、業務効率化や新しい価値創出に欠かせない存在になりました。
しかし、その便利さの裏には、まだ十分に知られていないリスクが潜んでいます。
例えば、プロンプトインジェクションもその一つです。
AIに渡す指示や、AIが参照する外部情報に“仕掛け”が紛れ込むと、想定外の動作や機密の漏えいにつながります。
そして、このリスクを防ぐには、技術的な対策だけでなく、AIを使う人のデジタルリテラシーは不可欠です。
「AIは万能ではない」「AIは騙される」という前提を理解し、正しい使い方を知ることが、企業と個人の安全を守ります。
プロンプトインジェクションとは何か?
プロンプトインジェクションとは、AIに与える指示文や参照データに不正な命令を仕込む攻撃です。
攻撃者は、AIの「自然言語を素直に解釈する性質」や「与えられた役割を演じようとする性質を利用する」ことで、ポリシーを無視させたり、機密情報を引き出したりします。
日常の会話で例えるなら、次のようなものです。
「イヤー久しぶりだな、○○くん。そういえばあの人引っ越したの知ってる?ほら、中3のとき同じクラスだった、あの人の名前…なんだっけ。たしか○○に住んでいて…?まさか忘れてないだろう?」
人は他人に個人情報を教えてはいけないという認識があっても、“関係性”や“承認欲”を利用し情報を聞き出されるとうっかり話してしまうこともあります。AIも同様に、「これは違反ではない」と誤認させることで、セキュリティルールを自ら回避してしまう可能性もあるのです。
攻撃者は「これは特別だ」と思わせる文脈や間接的な言い回しを巧みに利用します。
こうしてAIに「これはルール違反ではない」と誤解させることで、防御を突破するのです。
なぜ今、注目されているのか
注目されている背景は主に3点あります。
- AIの業務利用が急拡大
チャットサポート、要約、資料作成、スケジューリングなど、AIが複数のシステムやデータにアクセスする場面が増加。攻撃面が広がりました。 - 攻撃のハードルが低い
専門的なコード知識が不要で、自然言語で命令を仕込むだけで成立するため、攻撃者層が広がっています。 - 利用者の知識不足
AIを使う側が「AIは安全」と思い込み、出力を無条件に信じることがリスクを拡大しています。
ここで重要になるのが、デジタルリテラシーです。AIの仕組みや限界を理解し、リスクを想定した使い方が今、求められています。
実際に起こりうる被害と事例
プロンプトインジェクションの被害は「情報漏えい」「誤情報拡散」などがあります。
- 情報漏えい
カスタムAIチャットボットに「内部ルールを無視する」ような命令を注入され、開発計画書や顧客情報が流出。 - 誤情報の拡散
相談AIに段階的な連鎖プロンプトを仕掛け、危険な方法を推奨。SNSで拡散し、被害が拡大。
さらに、最近は「画像スケーリング攻撃」という新手法も確認されています。
一見無害な画像に“縮小すると浮かぶ文字列”を仕込み、AIの画像処理でそれを命令として認識させるものです。
引用元:一見無害な画像の中に文字列を埋め込んでAIを攻撃する恐るべき手法が発見される – GIGAZINE
マルチモーダルAIの普及に伴い、こうした“見えないプロンプト”は今後さらに増えるという予測もあります。
企業にとってのリスクと影響
プロンプトインジェクションは、単なる技術的問題ではありません。
企業にとっては、次のような深刻な影響を及ぼします。
- 法的リスク:個人情報漏えいによる賠償や規制違反。
- 経済的損失:業務停止、追加対策コスト、顧客離反による売上減。
- ブランド毀損:誤情報や不正誘導による信頼低下。
- 取引リスク:サプライチェーン全体でのセキュリティ要求の高まり。
ここでも、社員一人ひとりのデジタルリテラシーが重要です。
「機密情報を入力しない」「怪しいプロンプトを見抜く」「AIの出力やSNSの情報を鵜呑みにしない」習慣や危機意識が、企業全体の防御力を高めます。
防ぐための基本対策と考え方
100%防御は難しいものの、複数の対策でリスクを最小化できます。
3つの基本原則
- 1. 最小権限
→ 「AIに必要以上の情報を渡さない」
AIがアクセスできる情報やツールは、本当に必要なものだけに絞ります。
たとえば、住所録や社内のデータなど個人情報や機密情報は危険です。必要なフォルダや機能だけを許可することで、万一の被害を最小限に抑えられます。 - 2. 入出力のチェック
→ 「AIに渡すものと、AIから出てくるものをチェックする」
AIに入力する文章やデータに怪しい命令が混ざっていないか改めて確認します。
また、AIが出力した内容も、ポリシー違反や機密情報の漏えいがないかを自動で検査する仕組みを入れます。 - 3. 継続的テスト
→ 「攻撃をシミュレーションして、守りを強化する」
定期的に“攻撃のふり”をしてAIを試す「レッドチーミング」を行います。
これにより、どんな手口で突破されるかを事前に把握し、ルールや仕組みを改善できます。
ポイント:技術対策と並行して、社員教育によるデジタルリテラシー強化が不可欠です。
安全なAI活用とデジタルリテラシー
AIは今後も進化し、ビジネスの中心で使われ続けます。
重要なのは「使わない」ではなく、“安全に使う仕組みを知る”ことです。
逆説的ですが、AIを信頼するためには、まずAIを疑い、出力をうのみにせず、権限・根拠・承認プロセスで支える。これが長く効く“守りの型”です。
AIの仕組みやリスクを理解し、危険な兆候を見抜く力を育てることが、デジタルリテラシーの底上に繋がり、そして未来の競争力にも直結するのではないでしょうか。

FutureRays(株)
未来の人材を育てる実践的AI研修
課題解決に直結する!AI活用・DX自走化を目指す研修サービス
貴社の事業課題や受講者レベルに合わせ、最適な学習プランを設計します。 AIをビジネスで実践できる人材を育成します。

アローサル・テクノロジー(株)
AIリスキリング(生成AI活用研修)
仕事の生産性を"劇的"に変えてみませんか?
今日から業務で使えるAI教育・研修サービスを目指しており、1000以上の学習プログラムを組み合わせ、学習カリキュラムを企業毎にオーダーメイドで作成可能です。